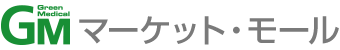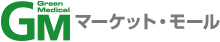【チェックリスト付き】薬機法を押さえた中古医療機器売買の正しい知識と方法とは?
更新日:2025年07月22日
 クリニックの開業や設備投資にかかるコストをできる限り抑えたい。その有効な選択肢のひとつとなるのが中古医療機器の導入です。しかし実際の導入にあたって、「価格の安さ」だけで判断して良いのでしょうか。導入後、後悔しないために本当に大切なのは、本来の性能が維持され、長く安全に使い続けられることです。
クリニックの開業や設備投資にかかるコストをできる限り抑えたい。その有効な選択肢のひとつとなるのが中古医療機器の導入です。しかし実際の導入にあたって、「価格の安さ」だけで判断して良いのでしょうか。導入後、後悔しないために本当に大切なのは、本来の性能が維持され、長く安全に使い続けられることです。
中古医療機器の性能と安全性を法的に支えているのが薬機法(旧薬事法)です。中古医療機器を取り扱う業者はこの法律に基づき、正式な許可のもとで安全管理を徹底する義務を負っています。ですから機器選びの成功は、薬機法を遵守した信頼できる業者を見極められるかにかかっていると言えるでしょう。そこで今回は、具体的なチェックリストを交えながら、安心して取引できる業者を選ぶためのポイントについて解説します。
薬機法(旧薬事法)と中古医療機器売買の基礎知識
 中古医療機器の売買や貸与など、取引における重要なルールを定めているのが薬機法(旧薬事法)です。薬機法は医療機器の品質・有効性・安全性を確保し、患者や医療従事者が安心して医療を受けられる環境を守ることを目的に定められています。
中古医療機器の売買や貸与など、取引における重要なルールを定めているのが薬機法(旧薬事法)です。薬機法は医療機器の品質・有効性・安全性を確保し、患者や医療従事者が安心して医療を受けられる環境を守ることを目的に定められています。
薬機法は新品だけでなく、一度市場で使用された中古医療機器にも等しく適用されます。人の生命に関わるからこそ、その安全性を法的な基準で改めて確認することが求められるのです。ここからは、中古医療機器を売買する上ですべての土台となる薬機法の考え方、その重要性についての基礎知識を詳しくお伝えします。
薬機法・薬事法とは?基本の定義と違いについて
2014年に「薬事法等の一部を改正する法律」が施行し、法令名も薬事法から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へ変更されました。
この改正における主なポイントは、医療機器の規制が抜本的に見直された点、そして「再生医療等製品」という新たなカテゴリーが作られたことです。特に医療機器に関しては、新たに「医療機器の章」が独立して設けられ、スマートフォンアプリのような単体のプログラムも規制対象として明確化されました。これは、法律が医薬品だけでなく、多様化する医療技術全体の安全性を確保する役割を担うようになったことを示しています。
中古医療機器の販売・購入に関わる法律の要点
薬機法では、中古医療機器の取り扱いを具体的にどう定めているのでしょうか。まず購入者が知っておきたい重要なルールとして、販売業者が守るべき「製造販売業者への事前通知義務」が挙げられます。これは、薬機法施行規則の第170条で、以下のように定められています。
(中古品の販売等) 第百七十条 高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、又は貸与しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。 2 (略)
出典: e-Gov法令検索『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則』
つまり、中古医療機器を販売する業者は、事前にその機器のメーカー(製造販売業者)へ「この機器を販売します」と通知する義務があるのです。これによりメーカーは自社製品の流通先を正確に把握し、リコールや改修などの安全性に関わる重要な情報を次の所有者へ確実に届けられるようになります。この通知義務は、ペースメーカーなど生命へのリスクが高い「高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ)」だけでなく、MRIや超音波診断装置といった「管理医療機器(クラスⅡ)」にも同様に適用されます(薬機法施行規則第178条による準用)。
したがって、信頼できる業者を選ぶには、扱う機器の種類にかかわらず、「製造販売業者への事前通知」というルールを遵守しているかどうかがひとつの判断基準と言えるでしょう。
【2025年に新たな改正が】改正点をわかりやすく解説
2025年5月14日、市販薬の販売方法や若者への販売制限など、国民生活に広く関わる改正薬機法が可決・成立しました。主な改正点は次の通りです。
| 主な改正点 | 概要 |
|---|---|
| 1. 市販薬の販売規制緩和 | 薬剤師などがICTを活用して遠隔で管理・情報提供することを条件に、コンビニ等での市販薬販売が可能になります。 |
| 2. 医薬品等の品質・安全確保の強化 | 若者のオーバードーズ対策として、20歳未満に対し「乱用等のおそれのある医薬品」の複数・大容量販売が原則禁止されます。 |
| 3. 医薬品等の安定供給体制の強化 | ジェネリック医薬品などの供給不足に対応するため、製薬会社に出荷停止時の事前報告や需給状況の管理が義務付けられます。 |
| 4. 創薬スタートアップ支援 | 「ドラッグ・ラグ」等の課題解消を目指し、「革新的医薬品等実用化支援基金」を設置して新薬開発を支援します。 |
| 5. 薬局・薬剤師業務の変革 | 薬剤師が対人業務に集中できるよう、医薬品のピッキングなど定型的な調剤業務の一部を外部薬局へ委託可能になります。 |
| 6. GMP適合性調査・査察体制の強化 | 医薬品の品質・安全管理体制を強化するため、製造販売業者に「品質保証責任者」等の設置が法的に義務付けられます。 |
| 7. 役員変更命令制度の導入 | 薬事に関する法令違反があり、国民の保健衛生に重大な影響を与える場合、国が企業の役員変更を命令できるようになります。 |
主な項目の施行期限は以下の通りですが、正確な日付は今後の政令で決定されます。
中古医療機器売買で押さえるべき重要なチェックポイント
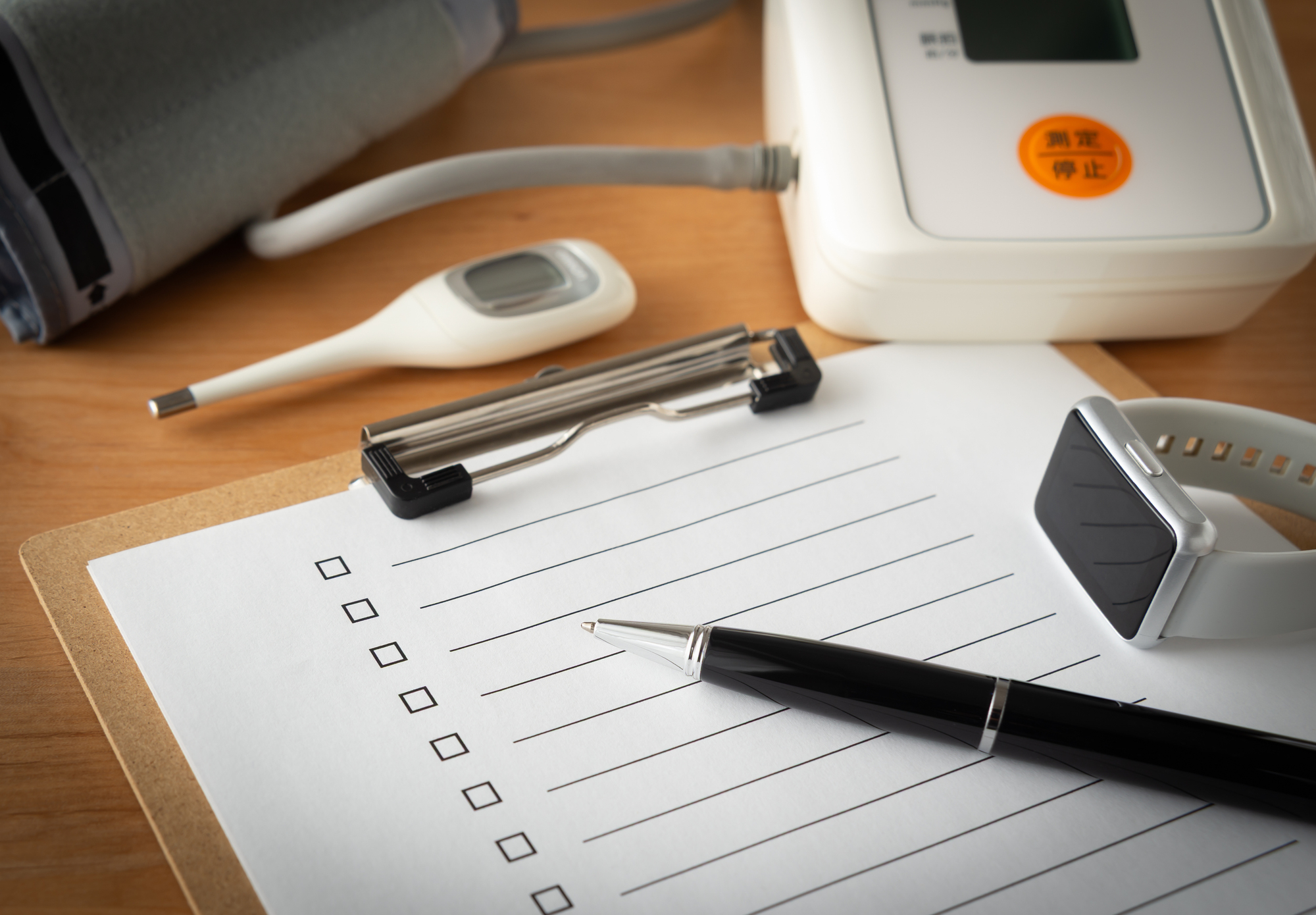 中古医療機器の販売・購入をトラブルなくスムーズに進めるためには、薬機法の知識が不可欠です。薬機法では「業として」行う売買に許可を定めていますが、見落としがちなのが、中古医療機器の購入などを日常的に行わない医師や医療機関もその対象である、という点です。このポイントを知らずに取引を行うと、思わぬ違反に繋がるリスクがあります。ここからは、安心して取引を終えるために必要なチェックポイントを解説します。
中古医療機器の販売・購入をトラブルなくスムーズに進めるためには、薬機法の知識が不可欠です。薬機法では「業として」行う売買に許可を定めていますが、見落としがちなのが、中古医療機器の購入などを日常的に行わない医師や医療機関もその対象である、という点です。このポイントを知らずに取引を行うと、思わぬ違反に繋がるリスクがあります。ここからは、安心して取引を終えるために必要なチェックポイントを解説します。
リスクの程度に応じた医療機器の分類と販売・貸与の手続き
中古医療機器を安全に購入するには、まずその機器がどのリスク分類に属するかを知ることが重要です。すべての医療機器は、まず国際的な基準である4段階のリスク「クラス(Ⅰ~Ⅳ)」に分けられています。日本の薬機法では、この4つのクラスを、販売に必要な手続きに応じて3つの大きなカテゴリー「高度管理医療機器」「管理医療機器」「一般医療機器」にそれぞれまとめています。
この分類に応じて、中古医療機器の販売・貸与には、生命へのリスクが高い「高度管理医療機器」には「許可」が、次にリスクの高い「管理医療機器」には「届出」がそれぞれ必要です。リスクの極めて低い「一般医療機器」については、特別な手続きは不要と定められています。各分類のリスクの程度と、必要となる手続きの概要は、次の表の通りです。
| 分類 | リスクの程度 | 販売・貸与の手続き |
|---|---|---|
| 高度管理医療機器(クラスⅢ、Ⅳ) | 副作用や機能の障害が生じた場合に、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。 | 製造販売承認申請 |
| 管理医療機器(クラスⅡ) | 副作用や機能の障害が生じた場合の影響が比較的低いもの。 | 製造販売認証申請 |
| 一般医療機器(クラスⅠ) | 副作用や機能の障害が生じた場合の影響が比較的少ないもの。 | 製造販売届出 |
中古医療機器の販売先の制限と購入許可
中古医療機器の売買は、その機器の種類やリスクの高さによって、販売先や購入者が法律で制限されています。まず販売する側は、機器が承認された使用目的や効果に反する使い方をされるとわかっている相手に販売してはならない、とされています。特に高度管理医療機器のようにリスクの高い製品は、不適切な使用が健康被害に直結する可能性があるため、販売先が医療機関や適切な資格を持つ事業者であることを確認するなど、慎重な対応が必要です。
購入する側にも厳格なルールがあります。一般の個人が購入できるのは、自己使用を目的とした家庭用の医療機器(例:マッサージ器や体温計)などに限られ、一度に輸入・購入できる数量も定められています。また、医師が使用するような医療機関向けの機器や、リスクの高い高度管理医療機器については、一般の個人が購入することはできません。したがって、クリニックなどが中古医療機器を導入する際は、医療機器販売業の許可を持つ正規の事業者を通じて、法に則った手続きで購入する必要があるのです。
中古医療機器の販売業者に必要な許可・資格の種類
中古医療機器の販売業者を選ぶ際に、確認すべき許可が2つあります。1つは薬機法に基づく「医療機器販売業・貸与業の許可または届出」、もう1つは古物営業法に基づく「古物商許可」です。
前者は医療機器を安全に取り扱うための資格、後者は中古品を正しく売買するための資格です 。信頼できる業者は、この両方を必ず取得しています。安全な取引のために、契約前にこれらの許可の有無を確認しましょう。
より詳しい内容は、【中古医療機器の購入時は要注意!】正規販売業者は許可制ですの記事でも取り上げています。
違反・トラブル防止と安全・法令遵守の重要性
 中古医療機器の無資格・無許可販売は、薬機法で厳しく禁じられており、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金(薬機法第84条等)といった罰則も定められています 。そのリスクは販売者だけのものではありません。許可のない業者から購入した機器は、品質が保証されず、万が一の事故が起きた際に患者の生命を危険にさらす可能性があります。安全な取引と医療のために、法令遵守の重要性をこの章で確認していきましょう。
中古医療機器の無資格・無許可販売は、薬機法で厳しく禁じられており、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金(薬機法第84条等)といった罰則も定められています 。そのリスクは販売者だけのものではありません。許可のない業者から購入した機器は、品質が保証されず、万が一の事故が起きた際に患者の生命を危険にさらす可能性があります。安全な取引と医療のために、法令遵守の重要性をこの章で確認していきましょう。
薬機法違反例と代表的な問題発生ケース
中古医療機器の取引では、残念ながら薬機法が守られていないケースも散見されます。代表的な違反例は以下の通りです。
これらの違反は、販売業者側が罰則を受けるだけでなく、購入者側にも大きなリスクをもたらします。例えば、無許可業者から購入した機器に不具合や故障が生じても、メーカーの保証や修理サポートは一切受けられません。また、万が一その機器が原因で医療事故が発生した場合、機器を導入した購入者側も社会的な責任や法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「安いから」という理由だけで安易に手を出すと、結果的に大きな代償を支払うことにもなりかねません。細心の注意が必要です。
法令に基づく安全管理とリスク防止策
薬機法では、中古医療機器を取り扱う業者に対し、患者の安全を守るための厳格な安全管理体制と、違反を未然に防ぐためのリスク防止策を講じることを義務付けています。
安全管理の体制とは、販売する機器の品質・有効性・安全性を維持し、常に正しく使用できる状態を保つための取り組みです。正規の業者は次のような管理体制を整えています。
リスク防止策とは、法令違反や取引上のトラブルを避け、安全な流通を確保するための対策です。購入者側も、業者が以下の対策を講じているか確認することが重要です。
薬機法の関係省庁と相談窓口
中古医療機器の売買を規制する薬機法は、国や都道府県が連携して運用しています。厚生労働省が法律全体の方針を定め、専門機関であるPMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)が審査や安全対策を担い、現場での許可や監視指導は都道府県・保健所が行う、という役割分担になっています。
もし中古医療機器の取引で薬機法違反が疑われる場合や、内容に不安を感じた際には、以下の専門窓口に相談・通報が可能です。それぞれ役割に応じた相談窓口を設けていますので、内容に合わせてご活用ください。
| 窓口名 | 内容 | 連絡先・受付時間 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 | 違反事案(ネット販売等)の通報 | 03-5542-1865(あやしいヤクブツ連絡ネット) メール:[email protected] |
| PMDA 一般の方向けご相談窓口 | 医薬品・医療機器全般の相談 | 03-3506-9425 月~金9:00~17:00(祝日除く) 音声ガイダンスで「1」→「2」で医療機器 |
| 都道府県薬務課・保健所 | 許可・届出、販売・流通、広告等の相談 | 各都道府県・市の薬務課や保健所 |
【チェックリスト】中古医療機器の適正売買に必要な確認項目一覧
中古医療機器の取り扱いにあたって、安全な取引かどうかを見極めるための具体的な確認項目を下記一覧にしました。薬機法では、販売業者に対して多くの義務を課しています。
下記チェックリストを使えば、業者がそれらの法令をきちんと遵守しているか、抜け漏れなく確認することができます。口頭での説明だけでなく、一つひとつの項目を業者に確認し、安心して取引できるパートナーかどうかを判断しましょう。
| ● | 販売業者が医療機器販売業の許可を有しているか | 薬機法第39条の3、販売業許可証の確認 |
| ● | 管理者が設置されているか | 薬機法施行規則第4条 |
| ● | 管理帳簿が作成・保管されているか | 薬機法施行規則第4条 |
| ● | 販売する医療機器の種類(管理医療機器・高度管理医療機器等)の確認 | 薬機法区分 |
| ● | 機器の品質・安全性に問題がないか(損傷・瑕疵の有無 | 薬機法施行規則第165条 |
| ● | 保守点検・メンテナンス記録があるか | 薬機法施行規則第170条・178条 |
| ● | 製造販売業者(メーカー)への販売通知を行ったか | 薬機法施行規則第170条・178条・191条第6項 |
| ● | 必要に応じてメーカーによる点検・修理を受けているか | 上記通知後、メーカー指示の遵守 |
| ● | 機器の使用状況・状態(稼働時間・使用環境等)が明示されているか | 購入者への情報提供(薬機法第40条の4) |
| ● | 取扱説明書・添付文書等が揃っているか | 購入者への情報提供義務 |
| ● | 医療機器の衛生管理・適切な保管がなされているか | 薬機法施行規則第4条 |
| ● | 不具合・事故等の報告体制が整備されているか | 薬機法施行規則第171条 |
| ● | 許可証・資格証等が営業所に掲示されているか | 薬機法施行規則第4条 |
グリーンメディカルは高度管理医療機器等販売・賃貸許可業者です
中古医療機器の購入で最も重要なのは、薬機法(旧薬事法)を遵守した信頼できる業者を選ぶことです。グリーンメディカルは、法律で定められた各種許可を正式に取得した正規販売業者です。 特に管理が厳しい高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可をはじめ、中古品取引に必要な古物商許可、自社での医療用具専業修理業許可も取得済みです。法令遵守の体制を整え、安全な医療機器のみを扱っておりますので、安心してご相談ください。
まとめ:中古医療機器の売買には薬機法(旧薬事法)が深く関わってきます
中古医療機器の取引に、薬機法(旧薬事法)の知識がいかに不可欠であるか、ご理解いただけたかと思います。「価格が安い」という理由だけで安易に無許可業者から購入してしまうと、機器の品質や安全性が担保されないばかりか、故障時のサポートも受けられず、最悪の場合は医療事故に繋がる可能性もあります。
リスクを避けるためにも購入者は薬機法の規制を正しく理解し、業者が「医療機器販売業」や「古物商」の許可をきちんと得ているかを見極める必要があります。安全な中古販売・購入はルールの遵守が重要です。正しい知識を身につけることが賢い選択にも繫がります。
グリーンメディカルへのよくあるご質問|薬機法に関して
Q1. 医師が自分のクリニックで不要になった医療機器を、知人の医師に1台だけ売る場合も許可は必要ですか?
はい。原則として許可または届出が必要です 。たとえ1回限りの取引で反復継続の意思がなくても「業として」の販売と見なされる可能性があります。安全な譲渡のためには、一度グリーンメディカルのような正規の専門業者にご相談いただくことをおすすめします。
Q2. インターネットオークションで安く売られている中古医療機器は買っても大丈夫ですか?
インターネットオークションでの購入は多くのリスクを伴います。オークションの出品者は、薬機法で定められた許可を得ていないケースがほとんどです。そうした機器は品質や安全性が保証されず、故障してもメーカーの修理・サポートを受けられないため、医療目的での使用は絶対におやめください。
Q3.購入を検討している業者が、本当に許可を得ているか確認する方法はありますか?
確認できます。優良な業者であれば営業所に「高度管理医療機器等販売業許可証」や「古物商許可証」を掲示しています。また、ウェブサイト等に許可番号を明記している場合がほとんどです。許可番号を明確に開示している業者を選ぶようにしましょう。
Q4. 「特定保守管理医療機器」とは何ですか?
保守点検や修理などの管理に、専門的な知識と技術を必要とする医療機器のことです。MRIやCT、超音波診断装置などがこれに該当します。この特定保守管理医療機器を販売・貸与するには、「高度管理医療機器等販売業・貸与業」の許可が必要となります。
Q5. 中古医療機器に、取扱説明書や添付文書は必ず付いていますか?
信頼できる正規の販売業者であれば、必ず付属しています。添付文書や取扱説明書は、その医療機器の正しい使用方法、保守点検の項目、禁止事項、緊急時の対処法などが書かれた非常に重要なものです 。これらが欠けている場合、その機器がどのような経緯で流通してきたかわからず、安全に使用できる保証はありません。付属品の有無も、良い業者を見分ける大切なポイントです。