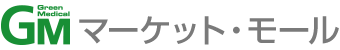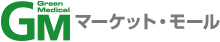医療機器市場での新旧大手交代劇をわかりやすく解説!
更新日:2025年04月21日
 日本の医療機器市場で、今まさに「新旧大手交代劇」と呼べるような大きな変化が起きています。かつて存在感を示した日立、パナソニック、東芝などの大手電機メーカーが、相次いでヘルスケア事業の縮小や売却に踏み切る一方、M&Aで事業を拡大する富士フイルムや、協業を進めるソニーとオリンパス、さらにはAIなどの先端技術を武器とするベンチャー企業などが存在感を増しています。
日本の医療機器市場で、今まさに「新旧大手交代劇」と呼べるような大きな変化が起きています。かつて存在感を示した日立、パナソニック、東芝などの大手電機メーカーが、相次いでヘルスケア事業の縮小や売却に踏み切る一方、M&Aで事業を拡大する富士フイルムや、協業を進めるソニーとオリンパス、さらにはAIなどの先端技術を武器とするベンチャー企業などが存在感を増しています。
各社の戦略転換や技術革新、市場環境の変化など、さまざまな要因が絡み合う今、業界の勢力図が書き換わりつつあると言えるでしょう。
この記事では、目まぐるしく変化する医療機器業界の現状を、主要企業の具体的な動きやM&Aの事例などを交えながら、わかりやすく解説していきます。
日本の医療機器業界は今まさに下剋上?!
 2025年現在、医療機器業界は技術革新の大きな波に直面しています。AI診断支援、医療IoT、遠隔医療、ブロックチェーン、VR/AR、デジタル療法、予測分析など多様な先端技術が登場し、医療の質・効率向上と業界の勢力図塗り替えが進んでいます。旧来の大手が苦戦し、新技術を持つ企業や異業種参入組が台頭する中、業界地図は大きく変わろうとしています。その背景にある大手撤退の要因や、新技術普及の課題について見ていきましょう。
2025年現在、医療機器業界は技術革新の大きな波に直面しています。AI診断支援、医療IoT、遠隔医療、ブロックチェーン、VR/AR、デジタル療法、予測分析など多様な先端技術が登場し、医療の質・効率向上と業界の勢力図塗り替えが進んでいます。旧来の大手が苦戦し、新技術を持つ企業や異業種参入組が台頭する中、業界地図は大きく変わろうとしています。その背景にある大手撤退の要因や、新技術普及の課題について見ていきましょう。
主要電機メーカー撤退の背景と要因
安定した収益源を求めて多くの大手電機メーカーが医療機器分野へ参入した日本。2014年から15年頃、日立はヘルスケア事業を強化し、パナソニックはヘルスケア部門を外部資本で独立、また東芝はヘルスケア社を新設するなど各社が体制を整え、参入を加速させます。しかし、人命に関わる事業運営の難しさや本業との相乗効果(シナジー)を十分に生かせなかった点、さらには期待したほどの採算が取れなかったことなどが壁となり、近年これらの主要電機メーカーは事業の縮小や撤退を余儀なくされているのが現状です。
新たな医療機器の開発と普及を妨げる障壁とは
AIなど先端技術を用いた新たな医療機器を開発し、市場に普及させる道のりは容易ではありません。特に日本では、承認審査の長さ、臨床データ活用の難しさ、現場でのAI導入へのためらいなどが、イノベーションの課題として指摘されています。こうした状況下で開発力を発揮し、将来性を期待される企業はどこなのでしょうか。その一つの目安となる特許資産規模を見ると、キヤノンメディカル、テルモ、湯山製作所などが国内上位を占める一方、旧大手電機メーカーの医療部門は上位に名を連ねていないという状況です。
これらの課題や国内市場の今後の動向については「医療機器業界の勢力図が激変?! 国内市場の今後の動向と展望を読み解く」で詳しく解説しています。
3大電機メーカーの撤退理由とその影響
 かつて日本の大手電機メーカーにとって、医療機器分野は持続的な成長が期待される魅力的な市場でした。しかし、安定収益への期待を胸に参入したものの、ここ10年でその状況は一変します。日立、東芝、パナソニックという日本を代表する企業が、相次いで同分野からの撤退や事業の大幅な見直しを迫られる事態となっています。少子高齢化による成長期待や、本格参入を目指した多額の投資・再編があったにもかかわらずです。なぜこれら国内屈指のメーカーは戦略転換を余儀なくされたのでしょうか。
かつて日本の大手電機メーカーにとって、医療機器分野は持続的な成長が期待される魅力的な市場でした。しかし、安定収益への期待を胸に参入したものの、ここ10年でその状況は一変します。日立、東芝、パナソニックという日本を代表する企業が、相次いで同分野からの撤退や事業の大幅な見直しを迫られる事態となっています。少子高齢化による成長期待や、本格参入を目指した多額の投資・再編があったにもかかわらずです。なぜこれら国内屈指のメーカーは戦略転換を余儀なくされたのでしょうか。
ヘルスケア事業の分割に踏み切った日立
日立製作所は、近年ヘルスケア分野で大きな戦略転換を進めています。まず2021年、画像診断機器事業という大きな柱を富士フイルムへ譲渡。さらに2023年にはヘルスケア事業そのものを会社分割し、ハードウェアを中心とした従来の体制から大きく舵を切りました。
しかしこれは完全撤退ではなく、新たな領域への挑戦を意味します。2025年度内には塩野義製薬との提携を通じて、医薬品・ヘルスケア業界向けのDXサービス提供を開始する計画を発表しており、事業の軸足をデジタルソリューションへと移しつつ、新たな活路を見いだそうとしているのです。
グループのスリム化を進めるパナソニック
大手電機メーカーの中でも、比較的早い段階でヘルスケア事業の大きな見直しに踏み切ったのがパナソニックです。2014年には、医療分野における中核であったパナソニックヘルスケアの全株式を投資ファンドKKRへ売却しました。現在では家庭用電気治療器などを家電部門で扱うに留まります。
この動きは、2025年度末を目標に進められているグループ全体の機能集約やスリム化といった、経営資源の集中を図り競争力強化を目指す同社の長期的な戦略の一環と捉えることもできるでしょう。
キヤノンに医療機器事業を売却した東芝
深刻な経営問題を抱えていた東芝にとって、優良子会社東芝メディカルシステムズ(当時)の売却は再建への大きな一歩でした。2016年、キヤノンが買収し、翌年には金融子会社も売却しています。結果として東芝は主要な医療機器事業から完全に撤退し、経営資源を再建計画下の注力分野に集中させました。
一方、この大型買収を成功させたキヤノンは、取得した事業を2018年に「キヤノンメディカルシステムズ」へと社名変更し、医療事業を大きな柱に据えます。旧東芝メディカルの技術力と販売網を基盤に、得意とするCT分野では国内トップシェアを独走するなど事業を拡大させています。ただ近年、過去の投資に伴う巨額の減損を計上するなど、その舵取りの難しさもうかがえます。
M&Aや資本業務提携に生き残りをかける企業
 大手電機メーカーが相次いで撤退・縮小する一方で、医療機器業界では激しい生存競争を勝ち抜くため、M&Aや資本業務提携の動きが活発化しています。市場シェア拡大や事業基盤の安定化、新技術・販路の確保など、各社の狙いが見て取れます。これらの狙いを自社単独で達成するのは簡単ではなく、M&Aによる規模拡大を通じたコスト削減や効率化、異業種連携による新たな価値創出が不可欠となっています。変化する市場で成長機会を掴み、生き残るための戦略を練る企業の動きをご紹介します。
大手電機メーカーが相次いで撤退・縮小する一方で、医療機器業界では激しい生存競争を勝ち抜くため、M&Aや資本業務提携の動きが活発化しています。市場シェア拡大や事業基盤の安定化、新技術・販路の確保など、各社の狙いが見て取れます。これらの狙いを自社単独で達成するのは簡単ではなく、M&Aによる規模拡大を通じたコスト削減や効率化、異業種連携による新たな価値創出が不可欠となっています。変化する市場で成長機会を掴み、生き残るための戦略を練る企業の動きをご紹介します。
ソニーとオリンパスによる医療事業合弁のその後
エレクトロニクス大手のソニーと、内視鏡世界首位のオリンパス。この異色の組み合わせによる医療事業合弁会社「ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ」は2013年に設立されました。オリンパスの光学技術とソニーの4K・3D映像技術などを融合させ、より高度な低侵襲治療を支える先進的な外科手術用内視鏡システムなどの開発が期待されたものの、近年は厳しい市場環境にも直面しています。
親会社オリンパスの2025年3月期連結純利益見通しが、中国での医療業界に対する取り締まり強化に伴う内視鏡販売不振などを理由に大幅に下方修正されたことも、その一端を示していると言えるでしょう。
利益でキヤノン超えを果たす勢いの富士フイルム
富士フイルムのヘルスケア事業は好調です。2025年3月期には連結純利益で5期連続の過去最高更新を見込み、最終利益では4年ぶりにキヤノンを上回る可能性も出てきました。中国での医療業界への取り締まり強化といった懸念を乗り越え成長する背景には、日立の画像診断事業買収などM&Aによる事業基盤強化が高い収益性につながっている点も強みです。
加えて医療ITを筆頭に、X線・超音波診断分野でもトップシェアクラスの実力を誇ります。特に医療DXを支えるIT分野がデータ活用なども含め、同社の成長を牽引しているのです。
老舗家庭機器メーカーの革新とベンチャーの台頭
業界の変化は大手だけではありません。電子体温計などでおなじみのテルモがカテーテル治療分野で世界的な企業に成長したり、タニタがDXを推進したりするように、老舗メーカーも事業の多角化や変革を進めています。さらに今後は、ITやエレクトロニクス業界など、さまざまな異業種から独自の技術を活かした参入が一層増えることも予想されます。
加えて、近年特に注目されるのがAI技術を武器とするベンチャー企業の台頭です。AIを用いた診断支援技術を持つアイリス株式会社はその代表例で、多彩な顔ぶれが新たな担い手として登場しています。
医療機器の進化と循環を支えるグリーンメディカル
先端的な医療機器の導入が大学病院や地域の基幹病院で進むと、中古医療機器が広く活用されるきっかけになります。最新機器導入で高性能な機器が中古流通し、地域のクリニックや診療所でも、高度医療機器を手にしやすくなるためです。
私たちグリーンメディカルは、メーカーによる点検や整備で品質・安全性を確認した信頼性の高い中古医療機器を、導入しやすい価格でお届けしています。中古医療機器に新たな価値を与えること、それは私たちの大切な務めです。信頼性の高い中古医療機器の導入・更新をご検討の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
まとめ:テクノロジーの変革で再編が進む医療機器業界
今回は、テクノロジーの変革を背景に再編が進む日本の医療機器業界の現状を見てきました。かつて市場を支えた日立・東芝・パナソニックなど大手電機メーカーが、採算性やシナジーの問題から撤退・縮小する一方、M&Aや技術革新を武器に富士フイルム、キヤノンといった新たなプレイヤーが台頭し、業界地図は大きく変化しています。アイリスのようなAIベンチャーの登場やテルモ、タニタなど老舗企業の変革、中古市場の役割といった多様な動きも注目されます。変化の激しいこの業界から、今後も目が離せません。